朝ドラ「あんぱん」の第20週で新たに登場する六原永輔(ろくはらえいすけ)。藤堂日向さんが演じるこのキャラクターの登場により、視聴者の間では「永六輔そっくり!」と話題になっています。そんな六原永輔のモデルとなった永六輔さんは、いったい何をした人なのでしょうか。
結論から言うと、永六輔さんは戦後日本の放送文化を築いた多才なクリエイターです。放送作家、作詞家、ラジオパーソナリティ、エッセイストとして活躍し、「上を向いて歩こう」の作詞で世界的に知られる一方、ラジオ番組で半世紀にわたって日本人の心に寄り添い続けた「ラジオの申し子」でもありました。
永六輔が築いた放送文化の基盤
🏃♀️#あんぱんオフショット🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) August 17, 2025
舞台の稽古のシーンをモニターチェックする大森さんと藤堂さん👀
とっても個性的なコンビですが、これからの嵩の作家人生に大きな影響を与えるお2人です!#大森元貴 #藤堂日向 #朝ドラあんぱん 見逃し配信中📱https://t.co/O8UoD6F9Lt pic.twitter.com/eT8X15oL4a
テレビ黎明期を支えた脚本家
永六輔さんは1933年、東京・浅草の最尊寺の住職の息子として生まれました。早稲田大学在学中にスカウトされ、大学を中退して放送作家の道に進んだという、現代でも珍しい経歴の持ち主です。
その才能が最も開花したのが、1961年から5年間にわたって放送されたNHKの人気バラエティー番組「夢であいましょう」でした。この番組は、まだテレビが珍しかった時代に家族で楽しめるエンターテインメントを提供し、日本のテレビ文化の基礎を築いた記念すべき作品です。
永六輔さんは、この番組の脚本・構成を担当し、日本初のテレビバラエティ番組の形式を確立しました。毎月1曲の「今月の歌」を作り、これが後に数々のヒット曲を生む源流となったのです。
「六八コンビ」が生んだ不朽の名曲
永六輔さんの最も知られた功績の一つが、作曲家・中村八大さんとのコンビ「六八コンビ」による楽曲制作です。二人が生み出した作品は、戦後日本の音楽史に燦然と輝く名曲ばかりです。
最も有名なのは、1961年に坂本九さんが歌った「上を向いて歩こう」でしょう。この曲は国内で大ヒットしただけでなく、アメリカでは「SUKIYAKI」のタイトルで3週連続全米チャート1位を獲得し、日本の楽曲として初の快挙を成し遂げました。海外で評価された日本のポップスの先駆けとして、音楽史上極めて重要な作品です。
他にも「黒い花びら」(第1回日本レコード大賞受賞)、「こんにちは赤ちゃん」(第5回日本レコード大賞受賞)、「遠くへ行きたい」など、現在でも愛され続ける楽曲を数多く手がけました。これらの作品は、高度経済成長期の日本人の心情を的確に表現し、時代の空気を音楽に込めた名作として評価されています。
「見上げてごらん夜の星を」とやなせたかしとの出会い
朝ドラ「あんぱん」で六原永輔が手がけるミュージカルのタイトルでもある「見上げてごらん夜の星を」は、1963年に発表された永六輔さんの代表作の一つです。
この楽曲にまつわるエピソードが、やなせたかしさんとの運命的な出会いでした。1960年、永六輔さんが脚本・演出を手がけるミュージカル「見上げてごらん夜の星を」の制作において、まだ無名だったやなせたかしさんに舞台美術の仕事を依頼したのです。
やなせたかしさんの回想によると、永六輔さんは突然自宅にやってきて、「お願いがあってやってきました」といきなり仕事を依頼したそうです。この時が二人の初対面で、なぜ未知のやなせさんに依頼したのかは「今でも不明」とやなせさん自身が語っています。
この出会いがやなせたかしさんの人生を大きく変えることになり、後にアンパンマン誕生にもつながる重要な転機となったのです。
ラジオの申し子として半世紀の軌跡
日本初のフリートーク番組の先駆者
永六輔さんの真骨頂は、なんといってもラジオパーソナリティとしての活動でした。1966年に「夢であいましょう」が終了すると、活動の中心をラジオに移し、1967年から「永六輔の誰かとどこかで」をスタートさせました。この番組は2013年まで続く長寿番組となり、46年間にわたって多くのリスナーに愛され続けました。
永六輔さんは「日本初のフリートーク番組」とも言われる「昨日のつづき」(1959年)にも出演し、台本に頼らない自由な会話スタイルを確立しました。これは現在のラジオ番組の基本的なスタイルの原型となったのです。
全国行脚で築いた「心の交流」
永六輔さんのラジオ番組の特徴は、スタジオに留まらず、全国各地を巡り歩いて放送を行ったことです。自らを「旅の坊主」と称し、47都道府県を回って地方の人々との交流を深めました。
名物コーナー「七円ハガキの日」では、リスナーから届いた日常の風景を紹介し、永六輔さんが心温まるコメントを添えました。この「七円」という名前は、番組開始当時の郵便ハガキの料金に由来しており、一般の人々の声を大切にする姿勢を表していました。
こうした活動を通じて、永六輔さんは放送を通じて全国の人々と「心の交流」を築き、ラジオというメディアの可能性を最大限に引き出した人物として評価されています。
文筆家としての多彩な才能
200万部のベストセラー「大往生」
永六輔さんは、放送の分野だけでなく、文筆家としても大きな足跡を残しました。特に1994年に発表したエッセイ集「大往生」は、累計200万部を超える大ベストセラーとなりました。
この作品は、全国を旅する中で出会った人々の生死にまつわる言葉を集めたもので、高齢化社会を迎えた日本人の心に深く響きました。永六輔さんの「短く簡単な言葉で物事の本質を突く」文章力の集大成として高く評価されています。
100冊を超える著作活動
生涯にわたって100冊を超える著書を発表した永六輔さんは、エッセイ、評論、芸能論など幅広いジャンルで執筆活動を行いました。特に「芸人その世界」は、日本の芸能界の歴史と文化を深く掘り下げた名著として知られています。
また、社会問題にも積極的に発言し、尺貫法の復権運動や江戸文化の継承など、日本の伝統文化を守る活動にも取り組みました。
社会への貢献と文化的影響
政治への挑戦と社会的発言
永六輔さんは1983年に参議院議員選挙に比例代表区から出馬するなど、政治の世界にも関わりを持ちました。結果は落選でしたが、文化人として社会に対する責任を感じ、積極的に発言を続けた姿勢は多くの人に影響を与えました。
障害との闘いと最期まで続けた仕事
2010年にパーキンソン病を公表した永六輔さんは、病気の進行により歩行困難になりながらも、最期まで仕事を続けました。車椅子での移動や病院からの放送参加など、プロ意識を貫き通した姿は多くの人に感動を与えました。
2016年6月27日の放送をもって最後のレギュラー番組「六輔七転八倒九十分」が終了し、その10日後の7月7日に83歳で静かに息を引き取りました。
まとめ
永六輔さんは、戦後日本の放送文化を築いた偉大なクリエイターでした。テレビ黎明期には脚本家として番組制作の基礎を築き、作詞家としては時代を代表する名曲を数多く生み出しました。そして何より、ラジオパーソナリティとして半世紀にわたり全国の人々と心を通わせ、メディアの持つ「人をつなぐ力」を最大限に発揮した人物です。
朝ドラ「あんぱん」の六原永輔は、そんな永六輔さんの創造力と人間愛にあふれた精神を受け継いだキャラクターとして描かれています。やなせたかしさんの人生に新たな光を投げかける存在として、物語にどのような影響を与えていくのか、今後の展開が楽しみです。
永六輔さんが遺した「人と人をつなぐ」という志は、現代のSNS時代においても変わらず重要なメッセージを私たちに届けてくれているのです。


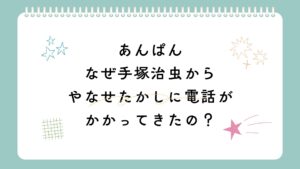
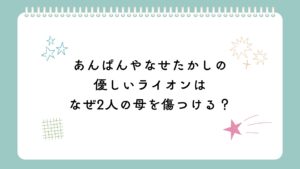

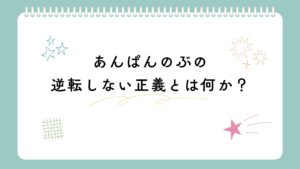


コメント