NHK連続テレビ小説「あんぱん」の核心を貫くテーマである「逆転しない正義」。この深い概念は、やなせたかしさんの壮絶な戦争体験から生まれ、後にアンパンマンというキャラクターに結実した、人類普遍の価値観を表しています。
物語の冒頭で嵩(北村匠海)が語った「正義は逆転する。信じられないことだけど、正義は簡単にひっくり返ってしまうことがある。じゃあ、決してひっくり返らない正義ってなんだろう。おなかをすかして困っている人がいたら、ひときれのパンを届けてあげることだ」という言葉に、その答えが凝縮されています。これは単なるドラマの台詞ではなく、やなせたかしさんが生涯をかけて到達した、人間の本質的な正義についての哲学なのです。
1. やなせたかしの戦争体験が生んだ「逆転する正義」への疑問
戦時下で体験した正義の逆転
やなせたかしさんにとって「逆転しない正義」の概念が生まれたきっかけは、第二次世界大戦での壮絶な体験でした。第二次世界大戦時、24歳で中国に出征したやなせさんは、飢えに苦しみながらも日本の正義を信じて戦っていました。
太平洋戦争に駆り出された時、この戦争は聖戦であり、「日本は苦しんでいる中国の民衆を救うために戦うのだ」と聞かされていたのに、戦争が終わったとたんに、正義の論理はあっけなくひっくり返って「日本軍は中国を侵略した」となったという体験が、やなせさんの価値観を根底から揺さぶりました。
戦争中は「鬼畜米英」と言った人が、負けたら「進駐軍万歳」に変わってしまう光景を目の当たりにし、やなせさんは「正義って何だろう?」と深く考えるようになったのです。正義のための戦いなんてどこにもないのだ、正義はある日突然反転するということを痛感しました。
飢餓体験が与えた深い影響
戦争で一番辛かったのは、飢えだとやなせさんは語っています。「戦争はとにかく腹が減る。人間いちばんつらいのはおなかが減っていることなんだ」と述懐し、当時は水みたいなおかゆやタンポポなんかを食べていたそうです。
「人間、飢えてくると、人を裏切ってでも何とか食べようとする。考えもおかしくなってくる」という体験から、やなせさんは戦争の原因は「飢え」と「欲」ではないかと考えるようになりました。腹が減ったから隣の国からとってこようとか、領土でも資源でもちゃんとあるのにもっと欲しいとか、そういうものが戦争につながるのですという洞察に至ったのです。
愛する弟の戦死という悲劇
やなせさんにとってもう一つの大きな悲劇は、愛する弟・千尋さんの戦死でした。非常に仲が良く、いつも兄であるやなせの後ろをついて歩いたという弟の死は、やなせさんの人生観に決定的な影響を与えました。
弟と同じように太平洋戦争で亡くなった日本兵は230万人とも言われており、アニメの主題歌『アンパンマンのマーチ』の歌詞は、戦争で生きる喜びを奪われた弟たち若者への鎮魂歌と解釈することもできます。
2. 「逆転しない正義」の本質とアンパンマンへの結実
絶対的正義としての「飢えた人を助けること」
やなせさんが戦争体験を通じて到達した結論は明確でした。困っている人、飢えている人に食べ物を差し出す行為は、立場が変わっても国が違っても「正しいこと」には変わりません。これこそが絶対的な正義なのですという確信でした。
アメリカにはアメリカの”正義”があり、フセインにはフセインの”正義”がある。アラブにも、イスラエルにもお互いの”正義”がある。つまりこれらの”正義”は立場によって変わりますが、困っている人、飢えている人に食べ物を差し出す行為だけは、どの立場から見ても正義であり続けるのです。
アンパンマンというキャラクターに込められた哲学
やなせさんは「おなかの減っている人を助けるヒーローが必要だ」と思いつき、それがアンパンマンの誕生につながりました。悪者を倒して去っていくだけのヒーローではおなかは膨れませんから、空腹で困っている人たちに、アンパンでできた自分の顔を食べさせるヒーローが生まれたのです。
アンパンマンに込めた”本当の正義”とは、「お腹をすかせた人を救うこと」でした。やなせさんは「正義とはかっこいいものじゃない」と譲らず、正義って相手を倒すことじゃないんですよ。アンパンマンもバイキンマンを殺したりしないでしょ。だってバイキンマンにはバイキンマンなりの正義を持っているかも知れないからという考えを貫きました。
自己犠牲という正義の本質
やなせさんの正義観において重要なのは、「正義とは痛みを伴うもの」という考えです。自分の身を犠牲にしてでも人を助けようとすることが、本当の正義であるとアンパンマンを通じて表現しています。
アンパンマンには弱点があり、汚れたり濡れたりすると力が出ません。つまり食べられない状態になるとパワーダウンするのです。それでもアンパンマンは、お腹を空かせた人に自らの顔を差し出します。この設定には、正義を行う者は弱く孤独であるという、やなせさんの深い洞察が込められています。
3. 現代に生きる「逆転しない正義」のメッセージ
普通の人にもできる正義
やなせさんは「正義って、普通の人が行うものなんです。政治家みたいな偉い人や強い人だけが行うものではない」と語りました。普通の人が目の前で溺れる子どもを見て思わず助けるために河に飛び込んでしまうような行為、それが正義だというのです。
ただし普通の人なので、助けに行って自分が代わりに溺れ死んでしまうかも知れない。それでも助けざるを得ない。この「愛と勇気だけが友だちさ」というメッセージには、やなせさんの人間観と正義観が凝縮されています。
現代社会への普遍的メッセージ
「正義というのは信じがたい、簡単に逆転するんですよ」というやなせさんの言葉は、現代社会においても重要な意味を持ちます。どの国も自国こそ正義であり、相手国が悪いとしか思っていない、その振りかざした正義こそ不安定なもの、あやしいものではないかという問いかけは、今日でも有効です。
人間の愚かさは、いつ、どこでも、自分が正しいという立場から、物事を考えていることですし、またその自分は正しいという立場を、自分で問い返すこともできません。そしてその立場で、いつでも自分の思い通りになることを求め、思い通りにならないものを排除することを考えています。
アンパンマンの永続的な意味
やなせさんによると、アンパンマンとライバル役のばいきんまんは共依存関係にあります。菌は食べ物を腐らせるが、食べ物がなければ繁殖できない。一方、パンは酵母菌からできており、菌なしでは存在しえない。つまり、パンと菌は「表裏一体」なのです。
アンパンマンはアンパンチでばいきんまんをやっつけるが、ばいきんまんは死なない。彼らの戦いは永遠に終わらないのです。悪人にも良い部分があり、善人にも悪い部分はある。嫌いだからと言ってやっつけてしまうと戦争になってしまうという深い洞察がここにあります。
まとめ
「あんぱん」で描かれる「逆転しない正義」とは、やなせたかしさんが戦争という極限状況の中で見出した、人類普遍の価値観です。それは「飢えている人に食べ物を与えること」「困っている人を助けること」という、シンプルでありながら絶対的な正義です。
この正義は、立場や国籍、思想信条を超えて、すべての人が共有できる価値観です。どんなに複雑な国際情勢や政治的対立があっても、目の前で苦しんでいる人を助けるという行為だけは、決して「悪」とは呼ばれることがありません。
のぶ(今田美桜)が軍国主義に染まり、戦争を正義だと信じて突き進んでいく姿は、「正義は逆転する」ことの恐ろしさを如実に示しています。しかし、物語の最終的な到達点は、そうした相対的な正義を超えた、絶対的で普遍的な正義の発見にあります。
やなせたかしさんが生涯をかけて伝えようとした「逆転しない正義」は、現代を生きる私たちにとっても重要な指針となります。大きな理念や思想に惑わされることなく、目の前の困っている人に手を差し伸べる。その小さな、しかし確実な愛の行為こそが、真の正義なのです。
「愛と勇気だけが友だちさ」というアンパンマンのメッセージは、戦争体験から生まれた平和への祈りであり、すべての人に向けた希望のメッセージなのです。

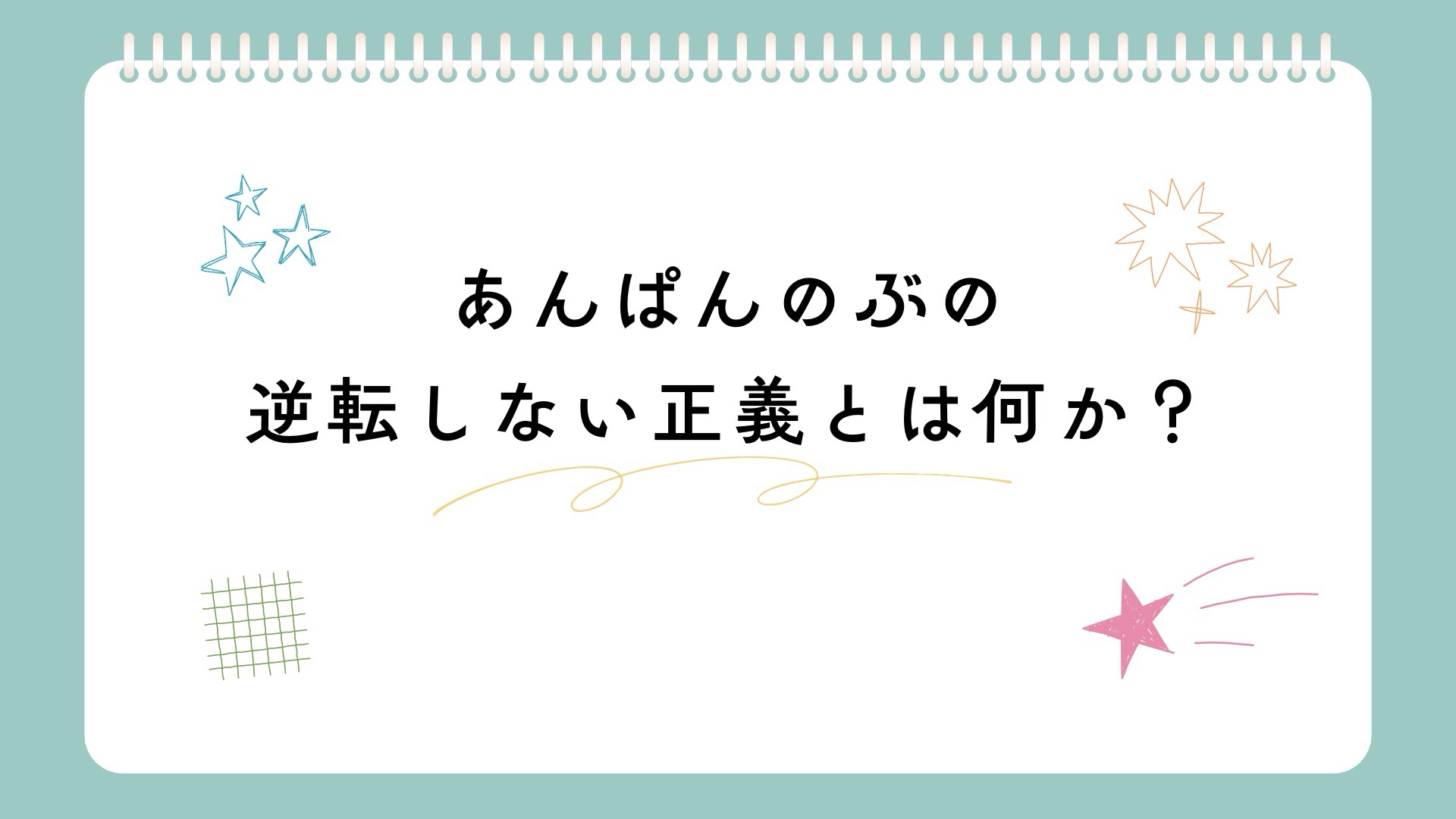
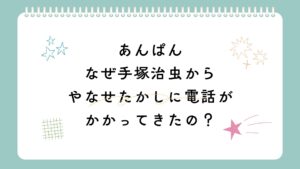
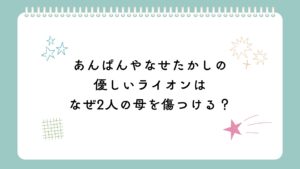




コメント