結論から申し上げると、「眠れる森の美女」と「いばら姫」は同じ物語をベースにしていますが、作者と成立時期、物語の内容、そして文化的背景に大きな違いがあります。「眠れる森の美女」は1697年にフランスのシャルル・ペローが書いた童話で、結婚後の恐ろしい続きがある大人向けの物語です。一方「いばら姫」は19世紀にドイツのグリム兄弟が編纂した童話で、ペローの残酷な結末を排除し、王子のキスで目覚めてハッピーエンドで終わる子供向けの物語となっています。 この2つの物語は、同じ民話を元にしながらも、それぞれの国の文化と時代背景を反映した異なる作品として発展しました。
世界中で愛されている美しい物語ですが、実は「眠れる森の美女」と「いばら姫」には重要な違いがあることをご存知でしょうか。今回は、この2つの物語の違いを詳しく比較し、それぞれの特徴と魅力について探ってみましょう。
眠れる森の美女といばら姫の違い
名作童話「眠れる森の美女」の魔女マレフィセントさんの誰も知らない物語、それがこのあと9時から地上波初放送でお届けする「マレフィセント」ですぅ🐰💞やさしーーーいファンタジーに心が洗われますよ⭐️ #マレフィセント #アンジー pic.twitter.com/7PoH5molKm
— アンク@金曜ロードショー公式 (@kinro_ntv) July 8, 2016
眠れる森の美女とイバラ姫の違いは作者と成立時期の違いにあります。
それでは見ていきましょう。
フランス版「眠れる森の美女」の誕生
「眠れる森の美女」(原題:La Belle au bois dormant)は、1697年にフランスの詩人・作家シャルル・ペロー(Charles Perrault, 1628-1703)によって書かれました。ペローはパリのブルジョア家庭に生まれ、ボーヴェ学院在学中から著述活動を始めた知識人でした。
ペローが活躍した17世紀のフランスは、ルイ14世の絶対王政時代であり、ベルサイユ宮殿に代表される華やかな宮廷文化が花開いていた時代でした。彼の童話は、この宮廷文化や貴族社会の価値観を強く反映したものとなっています。
ペローの童話集「過ぎ去りし時代の物語 教訓付き」には、「眠れる森の美女」以外にも「赤ずきん」「シンデレラ」「長靴をはいた猫」など、現在でも親しまれている作品が多数収録されています。
ドイツ版「いばら姫」の成立
「いばら姫」(原題:Dornröschen;KHM 50)は、19世紀初頭にドイツのグリム兄弟(ヤーコプ・グリム、1785-1863、ヴィルヘルム・グリム、1786-1859)によって編纂されました。グリム兄弟は言語学者であり、ドイツの民間伝承を収集・研究する学者でもありました。
グリム兄弟が活動した19世紀のドイツは、ナポレオン戦争の影響でドイツ統一への機運が高まっていた時代でした。彼らの童話収集活動は、ドイツの文化的アイデンティティを確立する一環としても重要な意味を持っていました。
グリム兄弟は、フランス人の子孫への取材や図書館でのペローの童話集の研究などを通じて、「いばら姫」を含む多くの童話を収集・編纂しました。彼らの目的は、学術的な民俗学研究と、ドイツの子供たちに適した道徳的な物語の提供でした。
時代背景が物語に与えた影響
約100年の時代差と異なる文化的背景は、2つの物語に大きな違いをもたらしました。ペローの時代は大人の娯楽としての文学が重視され、 グリム兄弟の時代は子供の教育と道徳的価値の伝達が重要視されていました。この違いが、物語の内容や表現方法に決定的な影響を与えています。
物語の内容と結末の違い
ペロー版の複雑で残酷な物語構造
ペロー版「眠れる森の美女」の最大の特徴は、王女が目覚めた後も物語が続くことです。グリム版やディズニー版で馴染みのある「王子のキスで目覚めてハッピーエンド」で終わらず、その後に恐ろしい展開が待っています。
ペロー版では、眠っていた王女が王子のキスではなく、100年が経って呪いの効果が切れたため自分で目を覚まします。そして2人は結婚し、オーロール(男の子)とジュール(女の子)という2人の子供をもうけます。
しかし、本当の恐怖はここから始まります。王子の母親である王妃が実は人食い鬼(オーガ)で、王子が留守の間に王女と2人の孫を食べようとするのです。王妃は料理人に「明日の昼食にオーロールを食べたい」と命令し、その後ジュール、そして最後には王女自身も食べようとします。
最終的に王子が帰還し、母親の行為が発覚すると、人食い王妃は自分の悪行が息子にばれてしまったことに動転し、ゲテモノが入った大きな桶の中に自ら飛び込んで死んでしまいます。
グリム版のシンプルで道徳的な構造
一方、グリム版「いばら姫」は、王子のキスによって姫が目覚め、「2人は死ぬまで幸せに暮らしました」で終わるシンプルな構造です。ペロー版の人食い鬼の話は完全に排除され、子供たちにも安心して聞かせられる内容となっています。
グリム版では、呪いをかける理由も異なります。ペロー版では単純に「招待されなかった」ことへの報復でしたが、グリム版では13人の魔法使いがいるのに金の皿が12枚しかなかったため、1人だけ招待されなかったという、より具体的で理解しやすい設定になっています。
また、グリム版では王子が城にたどり着く過程も詳しく描かれており、多くの王子たちが茨に阻まれて死んでいく中、呪いが解ける時期に到着した王子だけが城に入ることができるという運命的な要素が強調されています。
呪いの解け方の違い
ペロー版では、王女は呪いが自然に切れて自分で目覚めるため、王子の愛の力は直接的には関係ありません。むしろ、王子が現れたタイミングが偶然だったという設定です。
グリム版では、運命の王子の愛のキスによって呪いが解けるという、より一般的に知られているロマンチックな展開になっています。これは「真実の愛の力」というテーマを明確に打ち出した構成といえます。
文化的背景と価値観の違い
フランス宮廷文化の影響
ペロー版「眠れる森の美女」は、17世紀フランスの宮廷文化を色濃く反映しています。物語に登場する7人の妖精たちが王女に贈る「美しさ」「歌の才能」「踊りの才能」「楽器の演奏能力」などの贈り物は、当時の貴族社会で重視されていた教養と一致しています。
また、物語の後半部分に登場する人食い鬼の王妃の話は、当時の貴族社会の権力闘争や、姑と嫁の関係といった現実的な問題を寓話的に表現したものと解釈されています。これは大人の読者に向けた社会風刺の要素を含んでいます。
ペローの童話には各話の最後に「教訓」が付けられているのも特徴ですが、「眠れる森の美女」の教訓は「女性に向かってこの教えを説く、力も勇気もわたしは持ち合わせていない」と投げやりな内容になっており、ペロー自身も物語の複雑さに困惑していたことが伺えます。
ドイツ民衆文化とロマン主義の影響
グリム版「いばら姫」は、19世紀のドイツロマン主義と民衆文化の影響を強く受けています。ロマン主義では、感情、直感、そして真実の愛の力が重視されており、グリム版の「愛のキスによる救済」というテーマはまさにこの価値観を反映しています。
また、グリム兄弟は民間伝承の研究者として、庶民の道徳観と教育的価値を重視していました。そのため、ペローの残酷で複雑な展開を排除し、善悪が明確で子供たちに良い影響を与える物語に再構成したのです。
グリム版では、茨に囲まれた城や100年の眠りといった幻想的な要素が強調されており、これは当時のドイツロマン主義文学に特徴的な神秘性と自然への憧れを表現しています。
読者層の違い
ペロー版は主に宮廷の大人たちに向けた娯楽文学として書かれており、社会風刺や心理的な複雑さを含んだ大人向けの内容となっています。一方、グリム版は子供たちの道徳教育を目的とした教訓的な物語として編纂されており、分かりやすく純粋な内容に仕上げられています。
この読者層の違いは、現在でも2つの物語の受容のされ方に影響を与えており、一般的に知られているのはグリム版をベースにしたディズニー版の方ですが、文学研究ではペロー版の複雑さと社会性がより注目されています。
眠れる森の美女といばら姫の違いまとめ
「眠れる森の美女」と「いばら姫」は、同じ民話をルーツに持ちながらも、作者、時代、文化的背景の違いによって、全く異なる物語として発展しました。ペロー版は17世紀フランス宮廷文化を反映した大人向けの複雑な物語であり、グリム版は19世紀ドイツのロマン主義と道徳教育の価値観を反映した子供向けの純粋な物語です。
ペロー版の人食い鬼の王妃という恐ろしい続きがあることを知ると、一般的に親しまれているグリム版やディズニー版の美しさがより際立って感じられるでしょう。一方で、ペロー版の社会風刺的な側面や心理的な複雑さは、大人の読者にとって深い味わいを提供してくれます。
どちらの版も、それぞれの時代と文化の中で愛され、現代まで語り継がれてきた価値ある作品です。グリム版で育った私たちにとって、ペロー版の存在を知ることは、同じ物語でも異なる視点と価値観で語ることができるという文学の豊かさを実感させてくれます。
これらの違いを理解することで、単なる童話を超えた、各国の文化や時代背景を反映した貴重な文学作品としての価値を再発見できるのではないでしょうか。現在でも愛され続けている「眠れる森の美女」の物語が、実はこれほど奥深い歴史と多様性を持っていることに、きっと驚かれることでしょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。








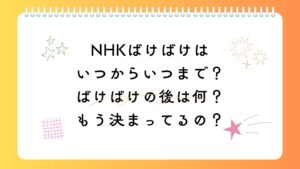

コメント